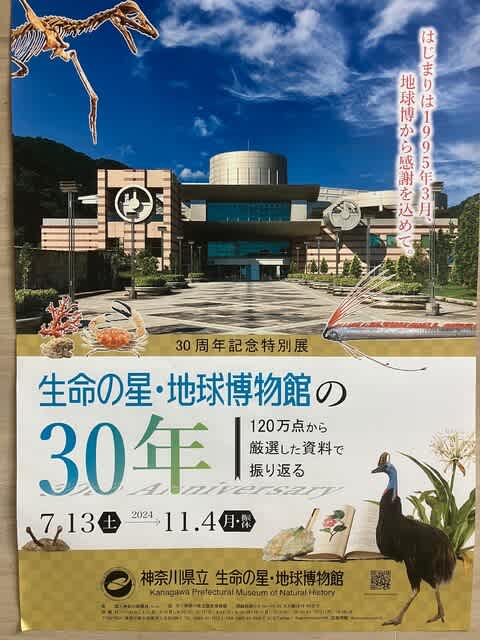【どうでもいい話】
そろそろキャンプ場の視察をしなくてはなりません。
06:30にバイクで出発。
交通渋滞は全くありませんが、バイクでも1.5時間くらいかかる。
今年のキャンプ地は過去最高の仕上がりになっておりましす。

日陰ゾーンもきれいに区画ができています。

いつの雨かわかりませんが水量が多い。
濁りが気になります、工事の関係でなければいいけど。

これで安心してキャンプできそうです。
08/13-14です。
帰り道は別ルートを通りましたが、道が荒れていて2回ほど大きく滑る。
帰りましてバイクを洗ってダラダラと過ごしてしまいます。
【バイク】
今のバイクは2018に買いましたのでもう7年も乗っている。
ひとつ前の白いバイク(NC700X)は6年、その前の黒いでっかい(XJR1200R)のも6年。
ここのところ大型バイクだけで20年乗り継いでいるのか。
このバイクを乗り継いでいるのは不満がないからだと思う。
前の白いのはとても遅かった。それ以外は完璧でしたが、あまりにも遅い。
その前のでっかいのは重すぎた。ガレージから出す気も出ないくらい重かった。
あと燃費も悪かった。
今のバイクは取り回しで困る重さというほどでもない。
恐怖を感じる程度には速い。
ハイオク指定が少しイヤ。
なんだかわからないバイクというのも少し気に入っている。
いわゆるバイクオタクに興味を持たれないのである。
そんな今のバイクも少し痛みが出てきた。
今後どうしようかなと悩むこともあったりなかったり。